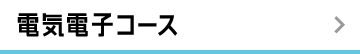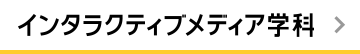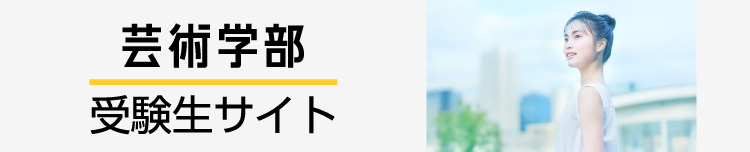対価と代償は似たような言葉のように思えるのだが、どう違うのだろうか。
自分の恥をさらすようだが、もしかすると、わたしはいままでまったく誤解していたのかもしれないことに気づいた。そんなのぜんぜん違うに決まっているじゃないという声が聞こえてきそうである。それでもめげることなく、後学のために書いておこう。以下の文章は自分が知らなかったことを、あたかも昔から知っていたかのように書く。こういくのを世間では「知ったかぶり」という。
対価というものは、得るものである。たとえば、いっしょうけんめい働いて会社に利益が生まれたとする。そうするとボーナスがもらえる。基本給は生活を支えるためのお金、ボーナスはそれ以上の働きに対する報酬、評価と思えばよい。対価はお金であるとは限らない。仕事をする、あるいは何か努力をして、ヒトのためになること、奉仕をすると、その後で対価が自分に支払われる。
それに対して、代償は、自分が支払うものである。何かを得たいと思って、その手段をいろいろ考える。目的を果たすには、何かをしなければならないことがわかってくる。その何かを代償という。例を挙げてみよう。
たとえば、何かの科目でクラスでトップの成績を取りたいとする。そのためには、たとえば教科書を声を出して100回読むという代償を支払わなければならない—というふうに使う。(あっているかな?)
あるいは、猛犬に吠えられるのをどうしても避けたいと思っているヒトがいるとする。そうすると、そのヒトは遠回りをして歩かなければならない。この場合は、遠回りをすることが猛犬に吠えられないという結果を得るために支払わなければならない代償である、ということになる。
このように、対価と代償は似ているようだが、使い方、つまり、使える文脈が違う。対価は自分がもらうもの。代償は自分が支払うもの、あるいは犠牲にするものである。
1つの文の中に対価と代償を共存させることもできるだろう。たとえば、
「対価を得たいとすれば、
それに見合う代償を支払わなければならない」
という文はどうだろう。
論理的には、この文は次の文と同値であることがわかるだろう。
「それに見合う代償を支払いたくなければ、
対価は得られない」
対価は誰でも欲しいと思うだろうし、代償は誰でもできることなら支払いたくないと思うだろう。どんなことがあっても支払いたくない代償というものも理論的には(つまり、可能性としては)考えられる。
20世紀初頭、数学の世界では排中律を認めると数学がおかしくなるのではと疑われたことがあった。そこで、排中律を認めない数学が生まれた。この学派のことを直観主義という。直観主義の数学は数学で使える道具を意図的にストイックに狭めたということができる。
ところが、排中律を使わないということは、背理法による証明を認めないということになる。背理法は数学の世界ではギリシャ数学以来ずっと使われてきた証明法なので、これを使ってはいけないとすることは「痛い」。数学で矛盾が起きる可能性がないという保証を得たいと思って始めた直観主義であるが、数学が進んでいく範囲を著しく制限するという代償を支払うことは数学にとって耐え難かったということだろう。
結局、大多数の数学者は直観主義のグループには入らなかった。
直観主義の数学は現在も研究されており、進展も見られる。それは、ふつうの数学とはちょっと毛色の変わった、不思議な数学である。