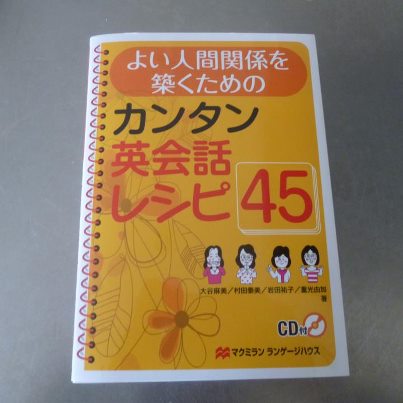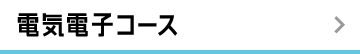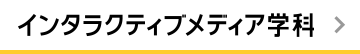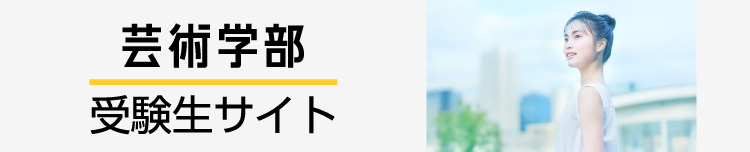学習院大学理学部数学科の飯高茂先生はこの3月にめでたく定年退職された。その飯高先生が今年のはじめに共立出版から出された楽しい数学書が3冊ある。いずれも、本格的な数学の専門書に進む前の「足慣らし」として読めるようにさまざまな工夫が随所にこらされた楽しい本である。これらの一連のご著書は、先生の学習院大学における長年の教育経験、中でも、数々のユニークな講義やゼミ生との共同研究の合間のやり取りから生まれたようである。ところで、その中の1冊、「体論、これはおもしろい」という本の前書きは、「ある小説ではルート君が登場する」という一文で始まっている。今回は飯高先生についての話ではなく、先生がここで「ある小説」と書かれているその小説について話してみよう。
その小説とは、小川洋子さんが2003年に新潮社から出された「博士の愛した数式」である。この小説はその後映画にもなった。
小説では、主人公である「博士」が同じく登場人物である少年を「ルート」と呼ぶ。ルートは、数式のルート(√)から来ているが、博士が少年をルートと呼ぶ理由はあまり数学的な理由ではない。ともかくも、それによって、ルートと呼ばれる少年が文学史上に登場することになった。
この小説は、数学者である博士とルートと呼ばれる少年、またその母である家政婦との間の愛の物語である。この小説において、主人公が数学者であるという設定は決定的な意味をもつ。主人公が男性で、その職業がたまたま数学者であるというだけではすまない、数学と深い関わりをもった物語が展開する。小説であるにも関わらず、純粋に数学の話が展開するのである。しかし、そうであるにも関わらず、読み進んでいくと、なるほどこれは愛の物語なのであると納得する。主人公である「博士」の数学に対する愛(これは数学者であれば当然もっているだろう)だけでなく、博士の人間に対する愛、深くて爽やかな愛、がこの物語のテーマである。
小説「博士の愛した数式」は、日本の数学小説の歴史において特殊な位置を占めている。それは、本格的な小説(まあ、これは、小説らしい小説というくらいの意味なのですが)において、数学がそのまま数学としての価値を保ちながら登場した最初のものではないかと思われるのだ。
2003年とい言えば、ちょうど東野圭吾さんによる小説「容疑者Xの献身」が、雑誌「オール読物」に連載されはじめた年でもある。東野さんは、映画やドラマにおいて数学者を登場させる作家として知られている。しかし、そのジャンルは小説というよりは推理小説、サスペンス物であると言ったほうがよいだろう。登場する数学者の数学に対する愛は当然語られるのだが、そこには「博士が愛した数式」のような暖かみはなく、むしろ、偏狂的な冷たい愛情である。それも数学者がもっている(あるいは持っていると社会で思われている)ある種の独特な雰囲気を表現し得ているとはいえるだろう。しかし、それは読者の数学に対する暖かい愛を呼び覚ますことはなく、むしろ物見遊山的な興味を引き出すのではないだろうか。そのようなものは、なるほど、いくら巧みに数学者の数学者らしさを表現し得ており、「いる、いる、そういう数学者、私も見たことある」という共感を呼び覚ますことはできても、それによって人間的な深い愛情を呼び覚ますことはない。
小川洋子の「博士の愛した数式」には、人間に対する愛、そして、その人間の太古からの営みの中で生まれ、人間の心を捉えて離さない「数学」に対する愛が満ちている。それは、まさに、私が「小説らしい小説」と呼ぶのに相応しい物語である。そのような共感に満ちた物語を数学という特殊職業分野を舞台として繰り広げたところに小川洋子の新しさがある。「博士の愛した数式」が、日本の数学小説の歴史において特殊な位置を占めていると私が思う理由がそこにある。
もうひとつ、この小説が扱っているテーマがある。それは「記憶」である。
主人公は、記憶障害という脳の障害を持っている。理系の学生(そして、そのナレノハテである数学者)の中には、日本史、世界史、英語などのいわゆる文系科目を「暗記科目」と呼んで毛嫌いするヒトが多い(ちなみに、「暗記」という用語は心理学にはない)。しかし、この小説を読むと、数学の研究においても人間の脳の「記憶」という機能が如何に大切であるかがわかる。数学こそは、主人公である博士が記憶障害というハンディを持ちながらも何とか毎日の希望を捨てずに生きていこうとする原動力であると思われるが、しかし、それと同時に、「記憶」という人間の能力の助けを借りずに数学をする主人公が置かれている状況を思うと、それが如何に困難な状況であるかがわかるのである。
数学に限らず、人間が人間らしい社会生活を営み、あるいは社会におけるさまざまな制度をうまく生活に生かし、あるいは家族を愛して生きていき、あるいは新しい価値を生み出していく上で、「記憶」という能力こそは基本的な能力であると思われる。それはあまりにも基本的であるがゆえに、私たちは、ふだんの生活において、その重要さを忘れがちである。しかし、記憶障害という状況を小説によって疑似体験することによって、人間にとっての記憶の大切さに気づかされるのである。記憶こそは、私たち人間が人間である証ともなる重要な能力である。
小川洋子「博士の愛した数式」(新潮社、2003)