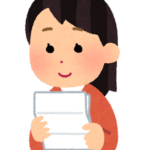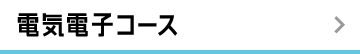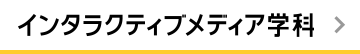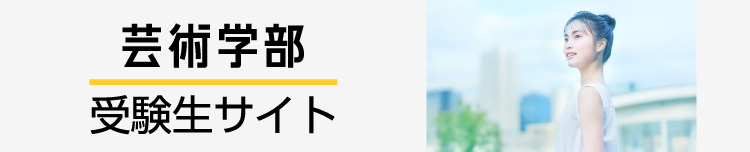*この記事は松中義大基礎教育教授が執筆しました。
リレー連載12月担当の松中です。
前回のリレー 連載は何を書こうか迷った末にCDを一枚紹介してお茶を濁した感がありましたが、今回も書くネタが思い浮かばず、苦し紛れに最近読んだ本を一冊ご紹介することといたします。
連載は何を書こうか迷った末にCDを一枚紹介してお茶を濁した感がありましたが、今回も書くネタが思い浮かばず、苦し紛れに最近読んだ本を一冊ご紹介することといたします。
ノーラ・エレン・グロース著(佐野正信訳)『みんなが手話で話した島』ハヤカワ・ノンフィクション文庫. 2022年刊.
1991年に出版されたものが、今年文庫化されて再販されました。裏表紙には以下のような紹介文が載っています。
アメリカ・ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害のある人が多く見られたこの島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごく普通に手話を使って話していた。聞こえない人も聞こえると同じように育ち、社交し、結婚し、生計を立て、政治に参加した。障害、言語、そして共生社会とは何かを深く考えさせる、文化人類学者によるフィールドワークの傑作。
アメリカ大陸がヨーロッパの人々に「発見」されて以降、多くの人々が入植しましたが、この島にはイギリス・ケント州ウィールド地方のある村から17世紀後半に集団的に入植が行われました。彼らの中で、どうやら聴覚障害が表れやすい遺伝的特性が受け継がれていたようです。また、入植地が「島」である、という特性から他所との交流が乏しく、そうした特性が長く維持されることとなりました。結果として、アメリカ合衆国全体の平均よりも20倍の確率で聴覚障害者が出現することになりました。これが何を意味するかというと、例えば、親戚に必ず一人は聴覚障害の人がいるとか、近所のよく行く店を経営している人、学校で親しくなった友人、といった確率で聴覚障害者に遭遇する、ということになります。
私の専門は言語学ですので、こうした環境におけるコミュニケーションがどのようなものだったか、ということに興味をそそられるわけです。本の題名にもなっていますように、この島では手話がいわば第二言語としての地位を獲得しており、近親に聴覚障害者がいる・いないに関わらず、健常者も子供の頃から(とてもローカルなものであるにせよ)手話を家族から学んでいました。結果として、健常者どうしで意思疎通を図る場合においても手話が使用されるケースも自然と発生しています。つまり、コミュニケーションにおいていわば「バリアフリー」な環境が成立していた、ということになります。
東京工芸大学芸術学部は「メディア芸術の拠点」ということを謳っています。人間がそのメッセージを外界に伝える手段として音声言語を発展させてきたわけですが、言語はまさに自分と他者を繋ぐ媒体(メディア)であるわけです。これは自明のことでありすぎるため、あまり省みられることがないのですが、この本を読んでみると、音声言語はメディアの一つに過ぎず、手話もまた同等にメディアとなり得ることがわかります。また、手話が単なるジェスチャーではなく、日本語や英語と同じく文法や語彙の体系を持つ言語であり、コミュニケーションの手段として同等に機能するということを実証している、と言えるでしょう。
歴史で「もしも・・だったら」を考えることはタブーだとも言われますが、もし人類の進化の過程で聴覚障害の発生の頻度がもっと高かったら、そしてそうした人々が人類の生存確率を高める何かしらの能力を兼ね備えていたら、、、マーサズ・ヴィンヤード島の事例がより普遍的な出来事になっていたかもしれません。近眼や左利きと同じくらいに発生していたら、メディアとしての言語は音声だけでなく手話も同じくらい普及していたかもしれません。
この島はその後19世紀に入ると本土との交流が盛んになり、人々の移動が増えた結果、固有の遺伝的特性は徐々に薄れてしまい、1950年代を最後に遺伝による聴覚障害者は姿を消しました。そればかりか、聴覚障害に対する偏見も持ち込まれることとなり、それまでの「バリアフリー」な社会が消滅することにもなりました。
この本のオリジナルは1985年に出版されました。すでに当事者である障害者はいない中、著者のグロースが島民へのインタビューや様々な記録を調査することでこの島の遺伝的特性、言語、社会の全貌を明らかにしようとする執念のようなものを感じる本でした。
もしご興味がありましたら、読んでみてください。
最後になりましたが、どうぞよいお年をお迎えください。