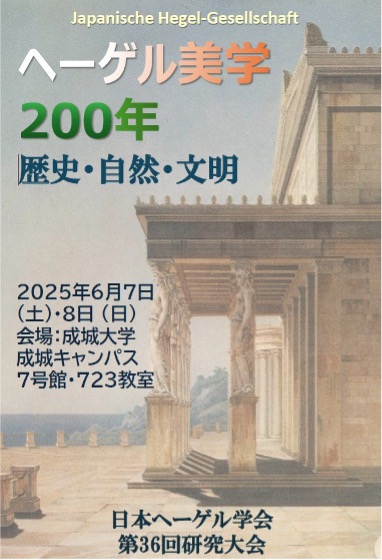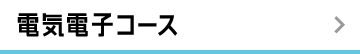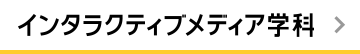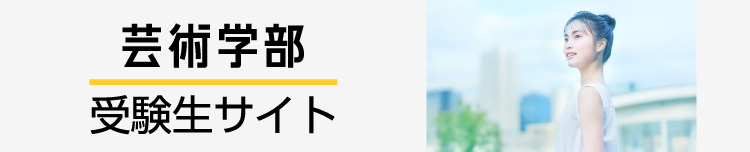*この記事は、今村みゑ子 基礎教育教授が執筆しました。
文学と絵画は関係が深い。古典文学研究の立場から『鳥獣戯画』甲巻を見ることで、新たな見方を提唱したい。
『鳥獣戯画』(『鳥獣人物戯画』とも)は4巻の絵巻で、それぞれ甲・乙・丙・丁巻と呼ばれる。甲・乙巻はほぼ同筆で12世紀、院政期の制作と見られている。通常の絵巻とは異なり詞書がないため、謎の多い絵巻とされている。甲巻についても、動物を擬人化して人間を諷刺したと見る説、年中行事絵の戯画と見る説等々、諸説紛々としている。しかし、それらは全体をざっと見るばかりで、それぞれの動物のしぐさの一つ一つの意味を捉えていない。
現代人の眼をもって眺めても、想像を馳せるばかりで意味はわからない。そこで、絵巻の制作された12世紀前後の資料を参照することによって、動物のしぐさの意味を考えていくこととする。すると、動物が人間の遊びを遊んでいる全体の戯画の中に、さらに場面毎に周到に戯画が仕組まれている重層的な戯画であることに気付く。
そこで、二つの場面を取り上げて、仕組まれた戯画を確認してみよう。
まず、兎方と蛙方に分かれての的弓ごっこの場面である(図1)。巻物を広げていくにつれ、見えてくるのは芦で作った枠に吊るされた丸い大きな蓮の葉の的で、芦で作った矢が一本刺さっている。的の両脇に控えた兎と蛙は当たった矢数を数える算刺(かずさし)、傍らで狐が火のついた大きな尾を、股をくぐらせ身体の前で掲げている。
この狐、実は自分の尾の火を松明に見立てて的を照らしているのである。その形状は12世紀に制作された『年中行事絵巻』の、宮中で侍たちが身体の前に掲げている大きな松明にそっくりである。狐は尾を燃やしているのではなく、いわゆる「狐火」を掲げているのである。狐火は、院政期の説話集『宇治拾遺物語』に火をくわえて走る狐の話もあるが、江戸時代の『一宵話』には「火とみゆるものは、彼が息なりけり。ヒョウト飛上ル時、口中よりフット息吹出づ。其息火の如く、ヒウヒウと光る。……撃レ尾出レ火など、古書にいひしは、口と尻との違ひなりと笑ひしも」とあり、絵巻のこの絵はまさしく「尾を撃ちて火を出(いだ)す」という「古書」の説に一致し、それが12世紀のこの絵巻で確認されるのである。
また、松明で的を照らすことは、平安時代の故実書『江家次第抄』の正月の賭弓の説明に「若及レ暗者、炬火三所、御前艮一所、射庭巽一所、的前一所」とあるように、暗くなると的の前にも松明を灯すのである。しかし、この場面は夜ではない。秋草が咲き乱れる白昼の野原での遊びである。つまり狐は狐火をもつが故に、ごっこ遊びの的弓で、的を照らす役を買って出たのである。ここには「狐火」を戯画化する作者のウィットに富んだ戯れ心が働いているのである。
次に法会ごっこの場面を見てみよう(図2)。導師は袈裟を掛けた猿で、蓮の花を挿した花瓶を置いた机を前に経を読んでいる。いかに熱心な読経であるかは、口から出る声が線で描かれていることで知られる。また、導師の近くにいる猿は、この法会を催した願主の役と見られ、袖で目頭を押さえ、読経の尊さに感涙を催す真似をしている。猿が導師や願主の役にふさわしいのは、『古今著聞集』の説話などに見られる、猿が人間に近いが故に、見様見真似で『法華経』の尊さを理解できる話とも関連する。
導師の前の本尊の仏には蛙が扮している。なぜ蛙なのか。蛙には水掻きがあり、それが、如来の三十二相の一つである「手足指縵網相(しゅそくしまんもうそう)」という手足の指の間にある薄い膜に似ているからである。衆生が救いの指の間から漏れないようにとの、如来の救済を表す相である。蛙にしか演じることのできない、蛙にふさわしい役なのである。
本尊の後ろに木立があり、枝に一羽の木菟(みみずく)が大きな眼をこちらに向けている。これは従来「梟」とされ、中には「梟だけが異質であり、すべての関係から離れている。そこに絵巻における語り手に近い意味を求めることは可能であり、梟はむしろ絵を見ている我々を見ぬいているのかも知れない」といった穿った見方もある。
しかしながら、これは梟ではない。頭部に耳状の羽毛が描かれているので木菟である。問題はそれによって意味が異なることである。当時の資料では梟と木菟の違いは、梟は声、それもおそろしげな鳴き声として認識され、木菟は「木の兎」という表記でも分かるように、耳状の羽毛を兎の耳に見立てられ、「聞く」という概念を付与されているのである。それは、例えば慈円の和歌(『拾玉集』)が、梟を「山深みなかなか友となりにけりさ夜更けがたのふくろふの声」、木菟を「いほりさす片山ぎしのみみづくもいかが聞きなす峰の松風」と詠み分けていることからも明らかである。そうしてみれば、木菟は猿の導師の読経を一心に聞いていると言わざるをえない。作者は当時の「よく聞く木菟」という概念を戯画化し、『法華経』の尊さを強調したものと言えよう。
法会の遊びは、12世紀、後白河法皇の『梁塵秘抄』に載る歌謡「法華は何れも尊きに、此の品聞くこそあはれなれ、尊けれ、童子の戯れ遊びまで、仏と成るとぞ説い給ふ」(品とは『法華経』「方便品」を指す)に通じる。『法華経』は子供の無邪気な遊びもまた善根を積み、成仏する手立てとなると説く。動物の法会ごっこもまたしかり、苦しみ多い「畜生道」の動物であればこそ、いっそうその成仏を祈る慈悲深い眼差しが注がれてよい。作者の意図もそこにあろう。ちなみに、的弓や印地では殺傷力のある武具・遊具の全てを植物で代用し、動物たちは遊びの楽しさのみを享受している。
以上、二つの場面で、動物に付帯する当時の概念が、機知に富んだ戯画として描かれていることを確認した。こうした表現は全体を通じて見出され、それこそがこの絵巻甲巻の本質である。そして、自らに付与されたコンセプトを無邪気に演じる動物たちは愛らしく描かれ、そこに作者の動物たちへの愛と、この絵巻の読者たち(おそらく子ども、さらには、この作者が僧である可能性があるので、寺の稚児たち)を楽しませようとする意図が感じられるのである。
*所蔵先リンク:世界遺産 栂尾山 高山寺 公式ホームページ
*参考文献:今村みゑ子『鴨長明とその周辺』「第二部第二編第八章」和泉書院、2008年