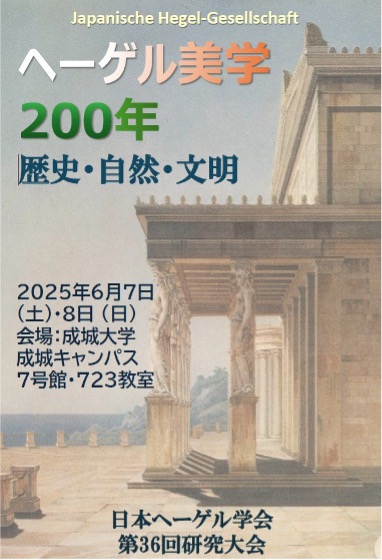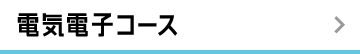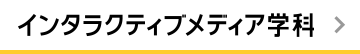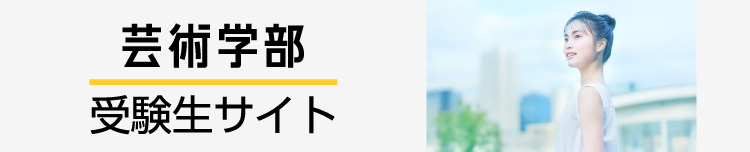みなさん、こんにちは。基礎教育課程の小田珠生です。
毎日暑いですね。今年の夏はオリンピックの観戦をテレビで楽しむなど、自宅で過ごす方が多いと思います。その「おうち時間」の一部を、読書をして過ごすのはいかがでしょうか。私は「日本文学」という授業を担当しているので、この機会に、授業で扱った際に比較的反響のあった作家をご紹介します。

「日本文学」は、古代から近(現)代までの日本の主な作家とその作品を体系的にご紹介する授業なのですが、授業の最後に書いてもらう感想を読んで比較的反響があったと感じるのは、樋口一葉をご紹介した回です。樋口一葉は、言わずと知れた現在の5千円札の肖像画となっている女性作家ですが、中学・高校の授業で人名と作品名(『たけくらべ』『にごりえ』など)は聞いたことがあるけれども、実際に作品を手に取って読んだことはない、という受講生の方が多いようです。
財務省は、樋口一葉を5千円札の図柄として採用した理由について、ホームページで「女性の社会進出の進展に配意し、また、学校の教科書にも登場するなど、知名度の高い文化人の女性の中から採用したもの」と説明しています。「女性の社会進出の進展に配意」した作家ということですが、それでは、樋口一葉が生きていた明治時代、女性はどのような環境下にあったのでしょうか。明治時代、日本の女性は「家父長的家族制度(原則として男性の家長に絶対的な権力としての戸主権が保証される制度)」と「公娼制度(特定の遊郭が公に営業権を保証される制度)」というふたつの制度に苦しめられていました(菅1999)。両者とも、女性への差別が認められる制度です。当時は女性が社会に向かって何かを主張することは極めて難しい、そんな時代でした。
そのような時代に、樋口一葉(本名、樋口奈津)は生まれました。子どもの頃は学校に通っていましたが、親が「女は学校に通う必要はない」と判断したため、11歳で泣く泣く学校に通うのをやめました。そのため、最終学歴は青梅学校小学高等科第四級ということになります。兄が夭折しただけでなく、17歳の時(1889年)、父親の事業失敗と死去という不幸があり、一葉は一家を背負う立場となると同時に、貧しさに苦しめられることとなります。19歳のときに小説家として生計を立てようと決意しましたが(当時の社会状況を考えると、かなり思い切った決断です)、当初は平凡な物語しか書けなかったため鳴かず飛ばずで、1893年から生活のために吉原遊郭の裏手で駄菓子などを売り始めました。そこで吉原の女性たちの苦しい生活を間近で見たことがきっかけとなり、一葉は突然人が変わったように非凡な作品を次々と生み出すようになります。
一葉が描いたのは、明治の女性に強い抑圧を与え続けた二つの制度の下、底辺に生きる女性たちの悲哀です。例えば代表作の一つである『たけくらべ』は、遊郭周辺の下町に住む少年少女の淡い初恋を描いた作品ですが、大人になったら遊女としての辛い現実が待ち受けている少女の、純粋な子ども時代の終わりが美しくも切なく描かれています。花魁の妹・美登里(14歳)は勝気な美少女で、僧侶の息子・信如(15歳)に密かに恋心を抱いています。しかし、信如は美登里が普段仲良くしている仲間のグループに入っているわけではなく、お互いになかなか素直に接することができません。大人になったら姉と同じように遊女になることが決まっている美登里と、僧侶の息子である信如が将来結ばれる可能性は無いに等しいのですが、まだ無邪気な美登里はそのことが分かっていないのです。
日本文学者のドナルド・キーンは、『たけくらべ』と、同時期にアメリカで女性作家によって書かれた『若草物語』を比較しています。『若草物語』は、19世紀後半のアメリカを舞台とするマーチ家の四人姉妹の成長物語ですが、ここでは、成長は希望です。身持ちの正しい娘は理想の夫を獲得する、というハッピーエンドが待っています。一方、『たけくらべ』において、成長は恐怖です。美登里が夫を持つことができないのは明らかで、自分の生涯を通り過ぎていく男たちに媚を売る生活が彼女を待っています(ドナルド・キーン2013)。
美登里はまだ自分に明るい未来が約束されていると信じて疑っていませんが、子ども同士の関係の背後では、実は吉原のカネに依存する地元(あるいはよそ者)の大人の論理が働いており、子どもたちはその世界から抜け出すことができません(前田1992)。
詳しい内容の紹介は割愛しますが、ある日突然「大人に成るは厭(い)やな事」と言ってふさぎ込んでしまった美登利の家の門に、造花の水仙が一輪さされ、それは信如が僧侶の学校に入るため家を出て行く日だったらしい…という場面で『たけくらべ』は終わります。別れと子ども時代の終わりを暗示する、美しくも哀しい場面です。
一葉の作品は、森鷗外や幸田露伴など文壇の重鎮に認められ、彼女は世間から注目されるようになりました。しかし一葉は、いくら注目されて人が寄ってきても、それは自分が女性だから物珍しいだけだ、と冷静に状況を分析していたようです。「われは女成りけるものを、何事のおもひありとて、そはなすべき事かは」――私は女だから、やりたいことがあってもそれを実現することはできない――と一葉は日記に書いています。そのような思いを抱きながら、1894年12月~1896年2月、14ヶ月という短い期間に、一葉は多くの名作を含む12作を次々と発表しました(その期間を、樋口一葉を研究していた和田芳恵は「奇跡の14ヶ月」と呼んでいます)。そして、1896年11月、結核で亡くなります。なんと24歳という若さでした。
明治時代、樋口一葉は弱者の立場にある女性の苦しみを、美しくも哀しい小説という形で社会にアピールしました。一葉の小説は論文ではなく文学作品なので、作中で彼女の主張があからさまに「私は〇〇だと思う」というように言語化されているわけではありませんが、そこには圧倒的な説得力があります。文語体なのでちょっと読みにくいかもしれませんが、現代語訳もあります。先日のオリンピックの開会式は、「多様性」をテーマとして前面に出したものでした。ぜひ、夏休み中に樋口一葉の作品を読み、現行の「あたりまえ」について考えてみてください。
【参考文献】
松浦理英子他訳(2004)『たけくらべ 現代語訳・樋口一葉』河出書房新社
樋口一葉(1949)『にごりえ・たけくらべ』新潮社
ドナルド・キーン(2013)『日本文学史-近代・現代編』中央公論新社
前田愛(1992)『都市空間の中の文学』筑摩書房
菅聡子(1999)『時代と女と樋口一葉』NHK出版
財務省HP