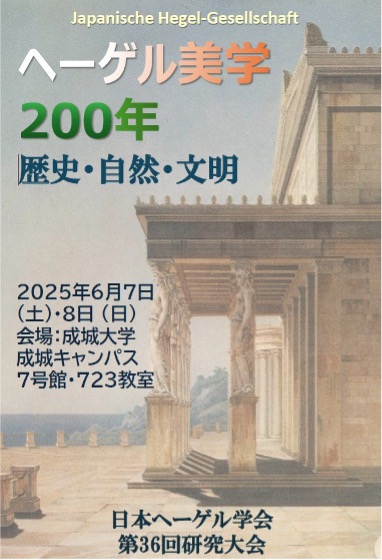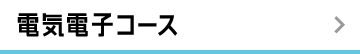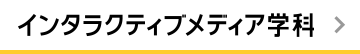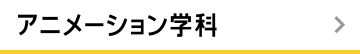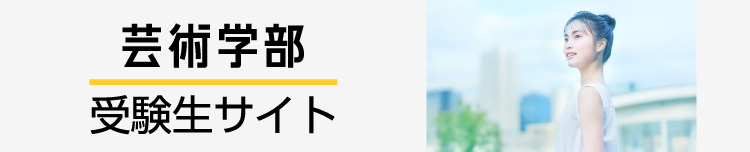今年度のリレー連載は、基礎教育の教員が目を引いたり、皆さんに紹介したい光景などをもとに文章を綴っていきます。今月は大森弦史先生にご寄稿いただきました。
こんにちは。基礎教育准教授の大森弦史です。
異例の猛暑がつづく2025年8月。「今月の一枚」を撮るために出かけるのが辛いので、自宅の庭でシャッターを切ってみました。

昨年に植樹したオリーブです。夏の日差しをたっぷり浴びてすくすく育ち、木はまだ小さいですが、ちゃんと実をつけるまでになりました。塩漬けにするのが今から楽しみです!
…これだけで話を終えるとさすがに怒られるので、今回は「オリーブと西洋美術」でちょっとだけ語ってみることにします。
暑さや乾燥に強く、実は食用になり、絞ると油がとれるオリーブは、大昔から地中海沿岸地域で栽培されてきました。オリーブ油の産出がヨーロッパ文明の発祥地である古代ギリシアに大いなる繁栄をもたらした歴史から考えても、文字どおり、西洋文明そのものを支えてきた、きわめて重要な植物であったといえます。
そのためオリーブは西洋文化に深く根ざした存在であり、歴史的にさまざまな意味を背負ってきました。例えば、身近な食用植物であったことから「豊穣」の概念と結びつけられましたし、戦女神アテナ(ローマ神話のミネルヴァ)が都市国家アテーナイ(現在のアテネ)にオリーブの樹をもたらした神話から、その枝は女神が司る「知恵」を表すものとなりました。そうしたなかでもっとも広く知られているのが、「平和」の象徴として機能してきたことでしょう。
「オリーブ=平和」の結びつきのはじまりは前5世紀ごろと考えられ、ギリシア神話の平和の女神エイレネはオリーブの枝を持物として表現されました。エイレネはやがてローマ神話の女神パクスと習合しますが、特にローマ帝政期において大いに信仰を集めました。戦乱を収拾して帝政をひらいた初代皇帝アウグストゥスは、平和と秩序の回復を願ってパクスを手厚く祀りました。オリーブの枝を掲げる平和の女神のイメージは、硬貨の刻印や彫像などを通じて広く流布していくこととなり、これが「オリーブ=平和」のつながりを強化した大きな要因となりました。

アウグストゥス時代の銀貨(前32-29年、銀製、大英博物館、ロンドン):表にアウグストゥスの肖像[左]、裏にパクス[右]が刻印されている。パクスは右手にオリーブの枝、左手にコルヌコピア(豊穣の角)を持つ姿で表現された。
またこの象徴関係は、旧約聖書『創世記』にあるノアの方舟の物語(6章-9章)とからめて、やがてキリスト教の文脈にも取り込まれていきました。
「…神は堕落した人々を洪水で滅ぼすとノアに告げ、彼に方舟の建造を命じた。ノアが方舟にすべての動物のつがいをのせた後、洪水は40日続き、地上の生き物をすべて押し流されてしまった。嵐がおさまって偵察に放った鳩がオリーブをくわえて戻ってきたことで、ノアは災いが去ったことを知った…。」――粗筋は大体こんな感じです。

『ニュルンベルク年代記』挿絵(1493年、木版・手彩色、folio 11r-1):洪水が起こる前の方舟建造の様子が描かれているが、右上には、オリーブの枝をくわえた鳩の帰還が予告されている。
鳩も「平和」の象徴としてよく知られていますが、これはどうやら、オリーブ由来で後からつけ加わったものです。初期キリスト教時代において、鳩はもっぱら「聖霊」になぞらえられていました。新約聖書では、イエスの洗礼(『マタイ福音書』3章16節)の際に降りてきた聖霊が鳩としてイメージされてきたからです。
その鳩が「平和」と結びついたのは、2〜3世紀のことと考えられています。この時代の神学者テルトゥリアヌスは、オリーブの枝をくわえて戻ってきたノアの鳩は神の怒りが収まったことを世界に告げたとし、それを天から送り出された神の平和をもたらす使いとして、洗礼における聖霊と結びつけて論じました。そこからオリーブの枝を伴う鳩は、死後の「平和」、すなわち魂の平安と安寧をもたらす存在として、カタコンベ(地下墓所)の墓碑などにさかんに描かれるようになったのです。

ローマ時代末期のキリスト教徒の墓碑(4〜5世紀ごろ、大理石、ヴァチカン美術館):キリストを意味するギリシア語ΧΡΙΣΤΟΣの最初の2文字を組み合わせたモノグラムを挟んで、オリーブの枝に乗った鳩が対称的に線刻されている。
こうして「オリーブ=平和」のつながりは、ヨーロッパ世界の二大源流であるヘレニズム(ギリシア文化)とヘブライズム(ユダヤ教・キリスト教文化)双方からより強靭なものとなりました。そしてそのヨーロッパ文化が近世〜近代の植民地主義を通じて世界中に伝播したことで、21世紀のわたしたち日本人も「オリーブ=平和」の象徴関係をなんとなく知るところとなっているわけです。

国際連合(国連)の旗にも、正距方位図法の世界地図をオリーブの枝が取り囲む図案が採用されています。凄惨をきわめた第二次世界大戦の苦い経験から、「平和な世界」への切実な思いが込められたデザインなのでしょう。そういえば今年は戦後80年を迎えます。昨今の不安定な世界情勢が少しでも良い方向に向かうことを願ってやみません。