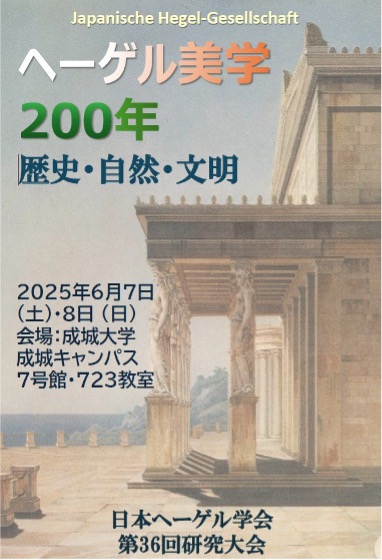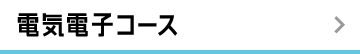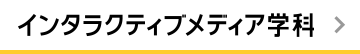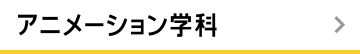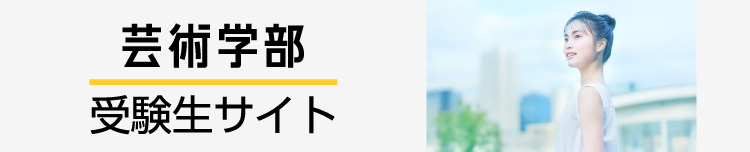今年度のリレー連載は、基礎教育の教員が目を引いたり、皆さんに紹介したい光景などをもとに文章を綴っていきます。今月は大島武先生にご寄稿いただきました。
こんにちは、大島 武です。
先月の小川先生に続いて学会の話題になりますが、国際パフォーマンス学会第43回年次大会に参加してきました。


パフォーマンスというと、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか。AIに訊いてみたら、ビジネスの文脈、芸術の文脈、日常会話&スポーツの文脈の三つに分類して丁寧に解説してくれました。でも、この学会の趣旨にど真ん中のものはなくてちょっと残念。要約して言うと、日常生活における振る舞い、自己表現について学際的に研究をしています。社会学のE.ゴッフマン、演劇学のR.シェクナ―などが有名ですが、日本では、そのシェクナ―のもとで学んだ佐藤綾子先生が1992年に学会を設立されました。佐藤先生は各種メディアにもよく登場するのでご存じの方も多いかもしれません。

国際パフォーマンス教育学会ホームページ:https://www.ipef.jp/
私はこの学会にもう20年以上お世話になっていて、現在、副会長を務めています。ビジネス、医療、教育、政治等さまざまな分野で活躍している人たちが、それぞれの自己表現について発表し、その内容について学術的に検討する実践発表は大会プログラムの大きな特徴で、毎年多くの学びがあります。今年は医療、教育分野からの研究発表、整体、美容分野からの実践発表があり、私は後者のコメンテーターを担当させて頂きました。最近の傾向として医療分野からの発表が多くなっています。情報化の時代、知識が表面的にフラット化して、昔なら「お医者さんがそういうなら正しいのだろう」で済む場面でも、ネットで調べて素人が突っ込むことが多くなりました。そうした背景もあり、医療関係者の間でパフォーマンス学への関心が高まっています。専門家受難の時代の反映とも言えるかもしれません。

年次大会は専門の研究者以外にも広く門戸を開いており、過去には本学学生も何人かオブザーバー参加しました。日頃の学びや創作活動とは全く違った体験、気づきがあったと言ってくれる学生が多かったです。また、「プレゼンテーション基礎演習A」ではパフォーマンスの理論をプレゼンテーション技術の解説に活かしています。あ、そうそう、新型コロナの影響で個人発表中心に切り替えていた「プレゼンテーション基礎演習A」ですが、今年からグループワークを完全復活させました。他学科、他学年の人たちと交流できる貴重な機会を提供していますので、まだ受けていない方はぜひ履修をご検討ください! ・・・あらあら、結局最後は担当授業の宣伝になっちゃいました。